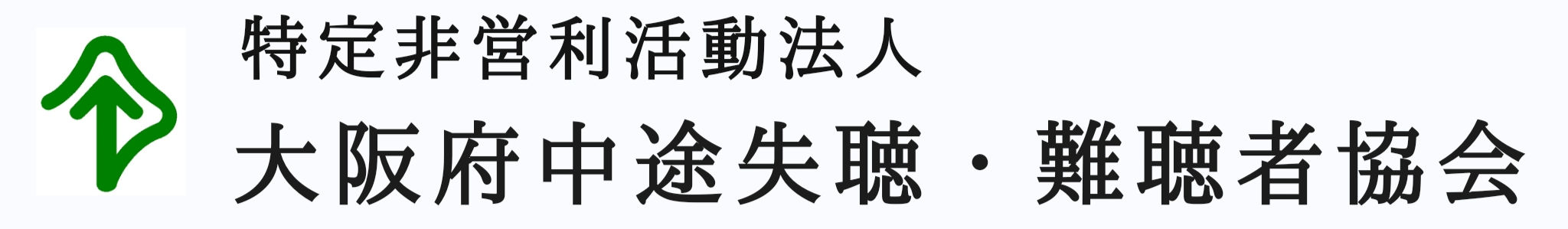活動
目的
・中途失聴・難聴者のコミュニケーション手段の普及とその促進を目指します。
・難聴者等の福祉と社会参加促進、難聴者等に対する啓発、難聴者等の生活、文化、教養の向上、及び会員相互の親睦。
活動概況
・大阪府要約筆記者の養成と派遣事業(大阪府委託事業)を実施、要約筆記の普及活動の実施。
・例会、女性部の集いの開催、年間6回の機関誌発行、行政機関との交渉、(一社)全難聴に加盟、関係団体との交流、耳マーク関連グッズの普及活動等を行っています。
難聴者の活動に思う 理事長から
「つながる声、ひろがる輪 ~難聴者とともに歩む社会を目指して~」
理事長から
私たちの協会が設立されたのは、昭和58年2月、今から40年以上前のことです。設立当時は、聴覚障害者といえば手話を使う「ろうあ者」というイメージが一般的で、中途失聴・難聴者の存在はほとんど知られていませんでした。また、要約筆記は、全国的に見てもまだ始まったばかりで、市町村レベルでは十分に定着していない時期でした。大阪府においても、要約筆記奉仕員の派遣制度がようやく始まったところで、当時は約10名の要約筆記奉仕員が、私たちの情報保障のために尽力してくださっていました。現代においてもなお、社会全体には「聴覚障害者=手話を使う人」という認識が根強く残り、中途失聴者・難聴者が多数を占めることすら、広くは知られていません。障害者差別解消法の施行をきっかけに、「聞こえにくいので、書いていただけますか」とお願いした際に、快く応じてくださる方が少しずつ増えてきたことに、社会の意識の変化を感じます。一方で、情報のやりとりに不自由を感じる場面もまだ少なくなく、今後さらに理解と配慮が広がっていくことを願っています。
協会設立当時のスローガンには、以下のようなものがありました
・輪と団結で聞こえの障害を克服しよう。
・同障の人に手をさしのべ、輪を拡げよう。
・要約筆記者の公費養成・派遣を求めよう。
・テレビに字幕を入れるよう求めよう。
・補聴器の公費支給を求めよう。
これらは、今も変わらぬ私たちの願いであり、目指す方向性です。
時代は大きく変わり、スマートフォンやパソコンなどを通じて、文字による情報を簡単に得られるようになりました。音声自動認識技術の進化により、字幕生成ツールや字幕電話「ヨメテル」のようなサービスも登場し、情報保障の方法は広がりつつあります。また、障害者差別解消法や障害者雇用促進法の改正を受け、都市部を中心に情報保障の重要性が徐々に認識されつつあり、要約筆記の活用場面も拡がりを見せています。とはいえ、全国的にはまだまだ課題も多く、一部地域では制度の周知が進まず、必要とされる支援が十分に届いていない現状もあります。さらに、ICTの進化が私たちに新たな選択肢を与えてくれる一方で、顔と顔を合わせて直接言葉を交わす“対面の交流”の価値も、これからも変わらず大切にしていきたいと考えています。
現代では、聞こえにくさを抱える人が高齢者の3人に1人と言われています。しかし「年を取れば耳が遠くなるのは仕方がない」と受け入れられ、声を上げることをためらう方も多く見られます。また、人生の途中で難聴になった方々も、職場や家庭、地域で事情を打ち明けられずに孤立することが少なくありません。高度難聴者でなければ障害者として認定されず、公的支援の対象とならない現状もあります。しかし、軽中度の難聴であっても、日々の困難は私たちと何ら変わることはありません。全難聴では、これまで厚生労働省に対して、障がい者認定基準の見直し(いわゆるデシベルダウン運動)を求めてきましたが、福祉財源の問題などから、軽中度難聴者の障がいとしての認定は依然として難しい状況です。私たちは、こうした「情報の障害」を広く社会に知ってもらうため、会員一人ひとりの働きかけが今こそ重要になっています。
私たち大阪府中途失聴・難聴者協会では、これからも要約筆記のさらなる定着と周知、ICT技術を活用した新たな情報保障手段の導入を進めるとともに、「直接会って話すこと」を大切にしながら、地域に根ざした活動を展開していきます。そして、社会のなかで誰もが自分らしく生きられる「共に生きる社会」の実現をめざし、皆さまと手を携えて歩みを進めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
大阪府中途失聴・難聴者協会
理事長 谷口学
協会のあゆみ
- 1983年(昭和58年)
2月27日 - 大阪府下の中途失聴・難聴者が集い、親睦と福祉の増進を目的に大阪難聴者連絡協議会が設立されました。
(前身は松原市を中心とした南大阪難聴者友の会)
「聞こえの保障」を求めて、その時のスローガンには「聞こえの障害の克服」・「同障者の親睦」・「要約筆記者の公費養成と派遣」・「ヒアリング ループとOHPの設置」・「テレビの字幕付与」・「補聴器の公費支給」などがうたわれています。
- 1984年(昭和59年)
- 大阪府難聴者連絡協議会から大阪府難聴協会に改称
- 1989年(平成元年)
- 大阪府難聴協会から大阪市内居住者を分離して大阪市難聴協会を設立
- 1993年(平成6年)
- 大阪府難聴協会から大阪府中途失聴・難聴者協会に改称
- 2007年(平成19年)
- NPO認可を受ける
特定非営利活動法人大阪府中途失聴・難聴者協会に改称
- 2014年(平成26年)
- 協会事務所を八尾市から大阪市天王寺区生玉前町の大阪府障がい者社会参加促進センター内に移設
- 2019年(令和元年)
- 協会本部を箕面市に移設。
支部事務所は大阪府障がい者社会参加促進センターで継続。
- 2020年(令和2年)
6月 - 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター開設に伴い、指定管理業務として指定管理者より要約筆記業務を受託。旧支部事務所は閉鎖。
大阪府の要約筆記者養成講座のあゆみ
平成24年度から要約筆記者養成講座を開始。また要約筆記登録奉仕員を要約筆記者にするためのステップアップ研修講座も同時開催。ステップアップ研修は平成25年度から28年度まで行い、約180名が要約筆記者課程を修了した要約筆記者課程84時間を終了したものと認定された。
大阪の要約筆記者認定試験の動き
平成25年度以降令和元年度まで大阪府、大阪市、堺市で合同の大阪要約筆記者登録試験を7回実施。 令和3年度以降は、大阪府、大阪市、合同の全国要約筆記者登録試験となり、第8回目を実施した。
(その他特筆すべき大阪における難聴者・要約筆記者に関するおおきな動き)
平成3年(1991年)・・・ 第9回全国要約筆記問題研究集会(大阪)
平成5年(1993年)・・・ 第1回大阪府中途失聴難聴者福祉大会(大阪)以降、2年に一度開催。
平成14年(2002年)・ ・ 第20回全国要約筆記問題研究集会(大阪)国際交流センター
平成19年(2006年)・ ・ 第13回全国中途失聴者・難聴者福祉大会(大阪・ドーンセンター)
平成29年(2016年)・ ・ 第34回全国要約筆記問題研究集会(大阪)大阪天満研修センター
昨今の大阪府中途失聴難聴者福祉大会の開催
令和4年(2022年)・・・第15回大阪府中途失聴難聴者福祉大会(大阪)
令和5年(2023年)・・・大阪府中途失聴・難聴者協会 40周年式典&記念講演会(大阪)
令和6年(2024年)・・・第16回大阪府中途失聴難聴者福祉大会(大阪)