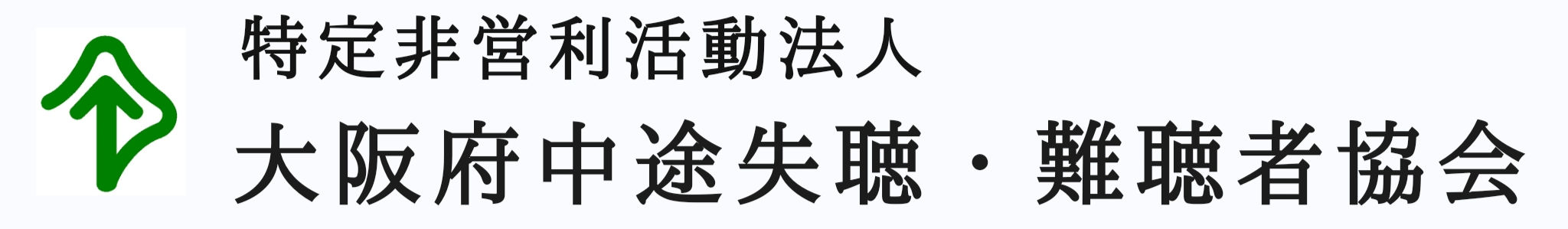中途失聴・難聴者の集会や会議の場などで使われるコミュニケーション保障手段の1つに要約筆記があります。
要約筆記には、手書き要約筆記とパソコン要約筆記の2つがあります。
また、利用される人数や内容により、ご利用の方法が異なります。
たとえば、講演会やイベント等、多人数が集まるところでは、プロジェクターとスクリーンを使用し、会場全体から要約筆記が利用できるようにする全体投影を行います。
利用される方が1~2人と少人数の場合は、ノートテイクという方法で、個別に要約筆記をご利用いただけます。
手書き要約筆記
全体投影では、要約筆記者4名1チームで、OHCおよびプロジェクター、スクリーンを使用し、ロールシートに油性ペンで書いた手書き文字を投影します。
ノートテイク時は、コピー用紙等に水性ボールペンを使用し、利用される方の隣で書いて伝えます。
OHC:オーバーヘッドカメラ(Overhead camera、OHC)

パソコン要約筆記
全体投影では、3~4人チームでプロジェクターとスクリーンを使用し、パソコンに入力した文字を投影します。
ノートテイクでは、ご利用される方の前にパソコンを置いて、その文字を読んでいただきます。
また、Zoom等を用いたオンラインでの研修会等にも遠隔での要約筆記を実施しています。

要約筆記者向けの情報(講座・研修などまとめたもの)
今年度の講座・研修情報を一覧で掲載予定です。
大阪府の要約筆記の流れ
当協会は大阪府要約筆記奉仕員養成・派遣事業の開始当初から大阪府の委託を受けております。現在は福祉情報コミュニケーションセンターの指定管理業務として指定管理者より委託を受け取り組んでいます。
大阪府の要約筆記奉仕員養成事業は昭和58年秋から始まりました。平成11年に当時の厚生省から要約筆記奉仕員養成カリキュラム52時間が各府県福祉担当部署に通知されました。
このときからパソコン要約筆記も加わり、全国的にカリキュラムが統一され手書き要約筆記とパソコン要約筆記奉仕員の養成・派遣事業が行われてきました。
平成23年3月末に厚生労働省から、要約筆記者養成カリキュラム84時間が通知されました。
これに伴い平成24年度から要約筆記者養成事業に切り替わり、平成26年から要約筆記者派遣事業に切り替わりました。
当協会の主要事業の1つとして取り組んでいます。
要約筆記者養成事業は手書きコースとパソコンコースの2コース(定員12名)があり、それぞれ84時間の受講が必要です。
両コース共に判定試験を行い、適性を見た上で受講可否を決定します。
要約筆記者になるには
84時間の大阪府要約筆記者養成講座カリキュラムを修了した後、毎年2月に行われる全国要約筆記者統一試験を受験、合格すると要約筆記者として登録し、派遣活動に従事できます。